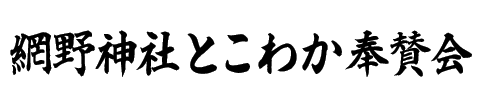
京都府京丹後市網野町網野788 (網野神社社務所内)
大正14年(1925)4月、丹後縮緬(たんごちりめん)同業組合竹野郡支部と竹野郡蚕糸(さんし)同業組合の関係者が協議して、本郡に織物(おりもの)の神(天照大神と天棚機姫大神)と養蚕(ようさん)の神(和久産巣日神と大宜津比売神)を奉祀(ほうし)することになり、竹野郡の中心網野町の網野神社に奉斎(ほうさい)しました。(時の府知事の斡旋もあって)織物神は京都紫野今宮神社御分霊を、養蚕神は皇居の紅葉山の養蚕神の御分霊を勧請(かんじょう)して合祀(ごうし)し、社名は大正天皇の皇后様である貞明皇后(ていめいこうごう)のお言葉のまにまに「蠶織神社(こおりじんじゃ)」と定められ、4月15日に網野町民、郡内養蚕業者数千人が参列し、盛大な鎮座祭が斎行されました。今日に至っても、毎年4月の中頃には織物業に携わる方々が中心となって、産業の振興と発展を祈願する盛大な神事が執り行われております。
現在の蠶織神社の社殿は、天明2年(1782)に建立されたもので、一間社流造(いっけんしゃながれづくり)の社殿の各部には江戸時代中期の匠による賑やかな彫刻が目を引きます。
蠶織神社は、その由緒に皇室とのご縁が非常に深いため、社紋は「菊」と「桐」になっており、社殿の棟にもそれらの社紋があしらわれております。大正11年(1922)に現在の網野神社の本殿と拝殿が新築されるまで、こちらが網野神社の本殿として崇敬されてまいりました。
●旧網野神社本殿
織物神と養蚕神を合祀し、大正天皇の皇后様である貞明皇后(ていめいこうごう)のお言葉のまにまに「蠶織神社(こおりじんじゃ)」となった。その由緒に皇室とのご縁が非常に深いため、社紋は「菊」と「桐」になっている。
天明2年(1782)に建立された社殿は、一間社流れ造り、三方に縁を廻らし、柱と頭貫上部には、龍や鳳凰、唐獅子、飛竜、象鼻などの彫刻で飾られて賑やかな江戸後期の神社建築である。
天照大神(あまてらすおおみかみ)
天棚機姫大神(あめのたなばたひめのかみ)
和久産巣日神(わくむすびのかみ)
大宜津比売神(おおげつひめのかみ)
織物の神(天照大神と天棚機姫大神)と養蚕の神(和久産巣日神と大宜津比売神)
・・・・・ 織物業の守護、技能芸能の上達、商売繁盛のご利益
こちらの四柱の神々はかつて網野神社の境内社として祀られておりましたが、大正14年1月22日に蠶織神社に合祀されました。
金山彦命(かなやまひこのみこと)・・・・ 鉱山の神(元小金神社)
高龗神(たかおかみのかみ)・・・・・・ 貴船神社の御祭神、水や雨を司る神(元小金神社)
大日孁神(おおひるめのかみ)・・・・・ 太陽の神、天照大神と同神(元大日孁神社)
若宇賀之女命(わかうかめのみこと)・・ 食物を司る神、豊受大神と同神(元大日孁神社)