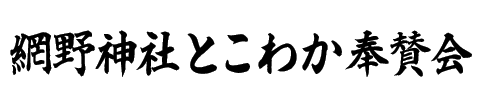
京都府京丹後市網野町網野788 (網野神社社務所内)
当社は延喜式内社(えんぎしきないしゃ)であることから創立は10世紀以前とみられています。元々は、三箇所に御鎮座されていたものを享徳(きょうとく)元年(1452)9月に現在の社地に合併奉遷されたと伝えられています。
現在の網野神社の本殿は一間社流造で、大正11年(1922)に建てられたものです。拝殿は入母屋造(いりもやづくり)の正面千鳥破風(しょうめんちどりはふ)と軒唐破風(のきからはふ)付きで、こちらも大正11年に本殿と同じくして建てられましたが、昭和2年の丹後大震災の被災により、昭和4年(1929)に再建されました。
日子坐王は第九代開化天皇(かいかてんのう)の皇子とされており『古事記』の中つ巻、第十代崇神天皇〔すじんてんのう(日子坐王の兄に当たられます)〕の御代に日子坐王は丹波の国(古くは丹後も丹波の国に含まれていました)に派遣されて土蜘蛛の首領「玖賀耳之御笠(くがみみのみかさ)」を誅(ちゅう)されたとあり、また別の記録にはその後、日子坐王は丹波に留まり、國造りをなされたとあります。さらに日子坐王は網野神社の他、丹後町の竹野神社(たかのじんじゃ)などに祀られ、網野銚子山古墳の主ではないかとも伝えられています。
伊耶那岐神(いざなぎのみこと)の禊(みそぎ)の時に成った上筒男命(うわつつのおのみこと)・中筒男命(なかつつのおのみこと)・底筒男命(そこつつのおのみこと)の三神を住吉大神と申し上げます。神功皇后(じんぐうこうごう)の新羅(しらぎ)遠征を守護したことから、特に海神として尊崇(そんすう)されています。
また、網野神社の住吉大神の縁起には、古代に日本海経由で来着したという説や近世になって河田金右衛門(かわだきんえもん)が泉州堺(現在の大阪府堺市)から勧請したという説などがあります。
水江浦嶋子神は、かつて網野村字福田の園(その)という場所に暮らし、毎日釣りを楽しんでおられましたが、ある時、海神の都に通い、数年を経て帰郷されました。今日まで伝わる説話や童話で有名な「浦嶋太郎さん」は、この水江浦嶋子神が、そのモデルとなっています。
網野には他にも嶋子をお祀りした嶋児神社(しまこじんじゃ 網野町浅茂川)や六神社(ろくじんじゃ 網野町下岡)、嶋子が玉手箱を開けた際にできた顔の皺(しわ)を悲しみのあまりちぎって投げつけたとされるしわ榎(えのき 網野銚子山古墳に存在)など、水江浦嶋子神に関わる史跡や伝承が今日までたくさん残っております。