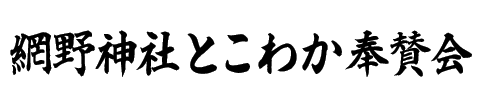
京都府京丹後市網野町網野788 (網野神社社務所内)
創立年月日不詳
『日本書紀』の垂仁天皇(すいにんてんのう)記二十三年には、「第十一代垂仁天皇の皇子誉津別王(ほむつわけのみこ)は三十歳になられても言葉をお話しになりませんでした。ある日、王が大空を飛ぶ白鳥をごらんになられて、『あれは何か』とお生まれになって初めてものを仰いました。その様子を父君である垂仁天皇はたいそう喜ばれて、天湯河板挙(あめのゆかわたな)にその白鳥を捕らえてくるようにお命じになられました。そこで湯河板挙は但馬國[(たじまのくに)(一説には出雲國)]まで追って白鳥を捕らえ、これを天皇の御前に献じました。それから王はこの白鳥と遊ぶうちに言葉を話されるようになられたのです。この功績を讃えられ、天湯河板挙には鳥取造(とっとりのみやつこ)の姓(かばね)を下賜されました。」とあります。
こうしたことから、早尾神社は病気平癒の御神徳があり、古くから人々より篤く信仰されております。
●網野地名の起源